
KRP誕生物語
KRP誕生物語 ~純民間インキュベータはこうして生まれた~
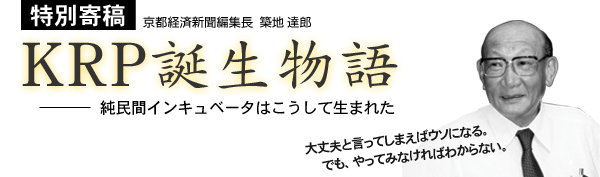
修学旅行生らに混じって、京都タワー展望台に上る。
東西南北の窓辺には、タワー創建時の40年前に撮影されたパノラマ写真が掛かっている。過去と現在の風景が眼前に広がる。
使命終えた“ガスタンク”

西側に掲げられた写真の右下に、ひときわ目立つ円筒形の白い建物が写っている。直径60m、高さ40mを超える、巨大建造物である。
大阪ガス・旧京都工場。昭和3年(1928年)に旧京都瓦斯の工場として建設され、京都市民に都市ガスを送り続けてきた基幹工場だった。巨大建造物は「五条七本松のガスタンク」と親しみを込めて呼ばれていた。
操業開始からちょうど50年目の53年(1978年)、京都工場は一部のガス供給施設を残して静かにその使命を終える。58年(1983年)にはほとんどの設備が撤去され、七本松通を挟んで6.5haもの巨大な遊休地が生まれたのだった。
「『リサーチパーク』をやらせて下さい」。
昭和62年(1987年)。大阪・御堂筋に面した大阪ガス本社ビル役員フロア。新分野事業開発担当役員の村瀬栄一とその部下の木村隆之は、副社長だった遠藤浩を前に、こう切り出した。
後に京都リサーチパーク(KRP)株式会社の最初の常務になる木村は、このとき京都工場跡地利用計画立案の主担当。10件を上回るさまざまなアイデアを立案して遠藤に提出していたが、いずれも“帯に短したすきに長し”だった。木村の説明の歯切れも悪かった。
ところが、このときはいつもと口調が違った。リサーチパークの意義、ベンチャーの街としての京都の地力、世界のリサーチパークの事情――。
「あの無口な木村が必死になって説明しよった」(遠藤)。
木村は遊休地化後の59年(1984年)から、リサーチパーク化の可能性を探るための勉強会を重ねてきた。経済界の若手リーダーとしてベンチャー育成の重要性を唱えていた堀場製作所社長、堀場雅夫(現会長)もいた。
木村はこの勉強会での成果を踏まえ、確信を持って遠藤への提案に臨んだのだった。

八方ふさがりの巨大遊休地
1985年のプラザ合意を経て極端な円高・カネ余りに陥った日本はこの頃、バブル経済へまっしぐらだった。
国内工場は次々に韓国や東南アジアに移転していく。広大な京都工場跡地を工場用地に使いたいという企業は皆無だった。
五条七本松という地域は洛中の都心部からそれほど遠くはないのだが、オフィスビルとしては微妙に足の便が悪い。また、副都心化するには規模が小さい。
全国的に流行し始めていた都市型レジャー施設やショッピングセンターなどが考えられたが、住宅地と近いことなどから実現は難しかった。
そうこうしているうちに、不動産価格が高騰し、マンション需要が爆発的に高まった。大阪ガス内部にも、マンション用地としてデベロッパーに売却するという案が出た。
ところが、都市ガス事業を所管する通産省資源エネルギー庁公益事業部(当時)の意向は違った。「公益事業として優遇され蓄積してきた遺産を安易に売却してしまうのは、いかがなものか」。
当時の都市ガスや電力は公益事業として地域独占を許される代わりに、通産省の厳しい監督下にあり、その意向は無視できない。
マンションでもなく、工場でもオフィスビル群でもなく、商業施設でもなく――。そんな八方ふさがりの状況の中からあぶり出されてきたのが、リサーチパーク案だったのだ。
よう分からんがやるしかない
木村がまくし立てるリサーチパーク案に対して、遠藤の第一印象は「よう分からん」。
リサーチパークというのは、誰に対して具体的に何をして、どのように稼ぐのか。大きな可能性を感じるが、どこか抽象的に感じた。
だが木村の熱弁に、若い頃から大手家電メーカーに伍して炊飯器などの家庭用ガス器具を売りまくってきた遠藤のマーケティング魂が動いた。
遠藤はその後数日、村瀬、木村が作った資料を必死になって読んだ。
どのように稼ぐかは、やはりはっきりとは見えなかった。だが、「成熟病にかかりかけていた日本経済全体がニュービジネスを求めている。しかも、純民間資本でのリサーチパークは日本で初めて。これなら通産省も文句は言わんだろう」――遠藤はこう考えることにした。
消極的選択だがこれで行くしかない。腹は決まった。
その直後の大阪ガス常務会。
今度は遠藤がまくし立てる番だった。一気に説明を終えた遠藤に、社長の大西正文が一言。「大丈夫か」。
「大丈夫と言ってしまえばウソになる。でも、やってみなければ分からない。他に検討した案はいずれも難しい。リサーチパーク案が認められないなら、跡地開発から撤退するしかないですな」と遠藤。
遠藤は「半分おどしでした」と笑う。
62年(1987年)10月、大阪ガス全額出資で京都リサーチパーク株式会社設立。遠藤は自ら、初代社長という片道切符を買った。
知能のコンビナート

それから2年後の平成元年(1989年)10月、第1期(東地区、48,000m2)の工事が終わり、リサーチパークが正式にオープンする。
KRP株式会社直営の1号館、2号館、アトリウム。京都府中小企業総合センター(現京都府産業プラザ)、京都市工業試験場(現京都市産業技術研究所 工業技術センター)、そして、京都市の外郭団体で京都大学工学部のエクステンションセンターとしての機能を持つ財団法人京都高度技術研究所(ASTEM)の各ビル。京都府と京都市の拠点が軒を連ねることになった。これは画期的なことだった。
一般的に都道府県と政令指定都市の建物が同じ敷地内に建設されることはない。互いのライバル意識が過剰に働くからだ。KRP開設にあたって、新しい統合的な産学連携拠点を設けるというプロジェクトに京都府、京都市とも趣旨は大賛同。ところが具体的に“同居”となると話は難航した。
「そこで、知事、市長に立て続けに会いに行って、直接談判したんです」と堀場が振り返る。
堀場はASTEM初代所長として、旧国鉄の列車予約システム「MARS」を開発した大野豊京大名誉教授を迎える人事を実現していた。行政の産学連携支援セクターと大学の拠点が同じエリアで融合し合うはずだった。「知能のコンビナート」(堀場)を実現しようとしたのだ。
「『これがやられへんのやったら、私は京都にいる理由がなくなる』――とまで思い詰めた」と堀場。その情熱と正論に、知事、市長はようやく重い腰を上げた。
その後、全国から行政マンの視察が相次いだが、この府と市の機関の同居は注目の的となった。
遠藤を先頭にした営業努力が実り、賃貸用の1号館、2号館には有力企業やベンチャー企業のテナントが集まった。オープニングイベントには、単独ヨット太平洋横断で知られる冒険家、堀江謙一が記念講演に立った。 追い風を帆に受けたスタートを念じてのことだった。

芋づる式のテナント誘致

だが、事業は必ずしも順風満帆とはいかなかった。
平成7年(1995年)早春。KRPは最大の経営危機に直面する。前年春に完成した4号館のテナントがなかなか決まらないまま年を越してしまったのだ。不況が長引いていたことに加えて阪神大震災や地下鉄サリン事件が起こり、社会不安が広がった。
入居を期待していた大口テナントとの契約が次々と反故になった。
そんなある日、社長の遠藤のところに企画開発部の2人の若手スタッフが1人の起業家を伴ってやってきた。若手スタッフは水野成容と元神久美子。起業家はエニアック・インターナショナル(京都市)の松川恵一。
デザイナー出身でCG(コンピューター・グラフィック)表現の草分けでもある松川が、マルチメディアビジネスにおける人材育成の重要さをとうとうと説く。
最初はデザイナーらしい奇抜な風貌の松川を胡散臭そうに眺めていた遠藤だったが、聞いているうちに「ここは若手の熱意に賭けるしかない」という考えになってきた。
水野、元神のプランは、フロアをできる限り小さく分割し、個人事業に近いような新興のマルチメディアベンチャーを数多く誘致するというものだった。そのために、まずキーマンを入居させ、芋づる式にたぐり寄せていく。従来の不動産業の発想にはない方式だ。
マルチメディアやITの世界は人材の力が剥き出しになる。人に着目した企業誘致こそが、可能性を引き寄せるはずだ。
マイクロソフトがネット接続機能を搭載したWindows95を発売するなど、折しもネット元年。
「やってみいや」。遠藤は2人の若手にこう告げた。
まずエニアックの松川、CG開発の先端を走っていたアンフィニ・エンタテイメント・テクノロジ(東京)の中村一、内田洋行(東京)の武幸太郎らを中心とするユニット「デジタルメディア京都」(DMK)をコアテナントとし、デジタルクリエーター向けのカンファレンスや塾を断続的に開いた。一方で水野らは、業歴や財務内容などは完全に不問にして、若い起業家たちにどんどん声をかけていった。
それを契機に、テナント数が爆発的に増えはじめた。テナント自身が親しい取引先を自ら誘致しはじめたのだ。 全財産はパソコン1台というような若い起業家が“居候”の形で居着いた場合も、追い出されることはなかった。むしろKRPのスタッフはこまめに声をかけ、新しいテナントに育てていった。
こうして平成8年(1996年)末には4号館もほぼ埋まり、翌年にはエリア全体で入居率98%に達するに至る。
「若い人のアイデアを年寄りが押さえたらあかん。そのことを教えてもらった」。引退後悠々自適の生活を送る遠藤は今、しみじみと語る。
KRPは現在ビジネスインキュベーション施設としてトップランナーとされる。前を走るものはいない。
だが、成功の体験はすぐに陳腐化する。トップランナーは常に、自らそれを乗り越えていかねばならない。
苦闘の道はこれからも続く。



















